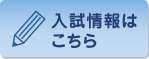地学部 朝日中学生ウィークリーに掲載
地学部 朝日中学生ウィークリーに掲載



11月25日(日),地学部は,東京大学本郷キャンパス小柴ホールで行われたJpGU(日本地球惑星科学連合) 2012年 秋の公開講演会に参加しました。
地球惑星科学(地学)は,太陽系の起源と進化を探り,地球史46億年の変動と進化,現在の地球の姿の解明を目指す基礎科学であり,地震や津波,火山噴火,気象災害,地球環境変動など,私たちの社会と密接に関わっています。この講演会では,富士山噴火など災害にみられる基礎科学の役割とその課題について考え,オーロラや恐竜の科学成果と将来の夢について解説することを目的に,JpGUによって企画されました(http://bit.ly/Nfy9aj 参照)。
各分野で活躍されている有名な熱い先生方の生の講義を聴くことができ,先端科学の知識はもちろん,多くの刺激を得たのではないでしょうか。また,この機会に合わせて,東大総合博物館を見学したり,一緒に講演会に参加した神奈川県立相模原青陵高校の地球惑星科学部の生徒と学食で食事をして交流を深めたりもしました。
地学部顧問
JpGU 2012年 秋の公開講演会
http://www.jpgu.org/whatsnew/20121125JpGU_sympo/index.html


先週のYSFHさんに続き、SSH数学ツアーの2週目として17日(土)に、茨城県の私立清真学園さんを訪問いたしました。先週同様、編集子が8月のマスフェスタで知己を得た同校高2の井上滉士さんを介した訪問で、井上さんの担当教員である法貴先生ならびに、数学科主任の大津先生に御尽力賜りました。
この日は丁度、動向のSSHの中間発表会(写真1)で、大学の先生方も審査員として多数来校されていました。開始が九時半ゆえ、本校生徒の参加が叶わず、編集子ひとりでの訪問となりました。

11月11日(日),地学部は,東京都立産業技術研究センター行われた,中高生の科学部活動振興プログラムの平成24年度成果発表会in東京に参加しました。この成果発表会は,これまで3年間の支援を受けてきたJSTの中高生の科学部活動振興プログラムの成果を発表するもので,同じく支援を受けている関東地域の学校が集まり,ポスター発表と活発な議論や交流が行われました。部からは,代表として水文班の4名が参加し,これまでの研究の概要と得られた成果を発表しました。多くの先生方や生徒たちとの議論により,アドバイスやつながりが得られたのではないかと思います。お疲れさまでした。

8月に既報の「マスフェスタ」にて、横浜サイエンスフロンティア高校(略称はYSFHとのこと)2年生の増田卓斗さんと知己を得た編集子。10日の午後、増田さんの研究の詳細を勉強すべく、本校高1の井上立之、恩田直登、増田康隆、山口哲の四君とともに同校を訪問致しました。恩田、増田両君は増田さんとは「マスフェスタ仲間」でもあります。
これは、同校数学科主任である高口健一先生と中山大輔先生のお骨折りによるものです。セミナールームで待機されていたのは増田さんに加え、同校の物理数学部の高1生である石井菜摘さん、紙谷将さん、村野あやねさん、両角光平さんでした。
お互いの自己紹介の後、まずは待望の増田さんの「ウラム螺旋」上の三角数が織り成す興味深い結果を詳細にお話頂きました(写真1)。これについては、先日、研修旅行で訪問されたマレーシアでも発表(英語による)されたそうです。
概要についてはマスフェスタにて既に伺ってはいた編集子でしたが、研究の苦心談や喜びも交えてお話を頂き、新たに胸が踊りました。そしてなにより、この研究の「美しさ」に心奪われた次第です。初めて聞く海城の生徒達も感に堪えない面持ちで聞き入っていま
した。
約1時間の発表の後、質疑応答に入りました。今まで、聞き入っていた海城の生徒は堰を切ったように猛然と質問を開始。決してこの機会を無駄にはすまいと、深い理解に努める様子がありました。のみならず、増田さんの研究において、「こういったケースではどうなりますか?私はこう考えますが」などと談論風発。その度に、「それについてはこういう結果がありまして…」と説明される増田さん(写真2)に一同舌を巻きました。「これもやりました、あれもやりました」ということなく、含羞みながら説明される姿に、増田さんの謙虚な人柄と悠々迫らぬ自信を垣間見た思いです。
宴ならぬセミナーもたけなわとなり、海城の4人が現在の興味関心を披露する機会を頂き、恩田君は「自身による定理のこと及び黄金角」について(写真3)、増田君は「自身による二次元における円順列公式の三次元への拡張」(写真4)を、山口君は「階乗進法の拡張」を、井上君は「折り紙の幾何」について、それぞれ説明致しました。YSFHの皆様から反響を頂け,一同の励みになりました。このことを編集子は自分のこと以上に誇らしく思いました。

11月4日、地学部は貝化石の採集とポットホール(甌穴)の観察•計測のため、和泉多摩川駅近くの多摩川河川敷に行きました。
以前にも、5月に多摩川で化石採集、6月に長瀞でポットホール観察を行っているのですが、なかなか研究に結びつくところまでは至りませんでした。そのため、生徒たちがもう少し戦略を考えた上で、今回改めて訪れてみました。化石に関しては、泥岩(シルト)層中に特徴的に貫入している砂岩層の前後で、産出化石や算出様式に変化があるかどうか。ポットホールに関しては現在形成中のものを含めて、河川の流れの方向に対してどのような形状になっているのかをより詳しく見てみました。まだまだカタチになるところまでは遠そうですが、今後の化石クリーニングやポットホールのモデル実験など、どのような展開になるか楽しみです。 地学部顧問

砂岩層を挟んで両側に場所を決め、化石採集する

11月2日、地学部有志5名は東京大学駒場キャンパスで行われた「地球惑星科学公開シンポジウム 海底・地中の旅、宇宙の旅」に参加しました。
内容は、地球外試料から探る物質進化、深海・地底の生態系、地球温暖化による成層圏循環の加速、生痕化石分析による古生態の解明、ダイヤモンドを用いた超高圧実験と多岐にわたり、参加した生徒それぞれが興味ある分野を見つけられるような構成となっていました。
放課後遅くから始まり疲れもあったでしょうが、適宜メモを取りながら2時間15分休みなくしっかり集中して聞いており、また、積極的に質問をする生徒もいて大変頼もしく感じました。特に高校生の質問には研究者をたじろがせたものもあり(同じ質問を修論発表会で教授にされたと言っていました)、ぜひ一緒に研究しようと誘ってくださっていました。生徒たちも最新の研究の一端を垣間見、刺激に満ちた有意義な時間となったのではないでしょうか。
地学部顧問

東京大学駒場キャンパス正門前で記念撮影