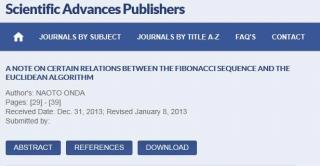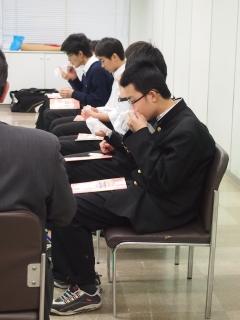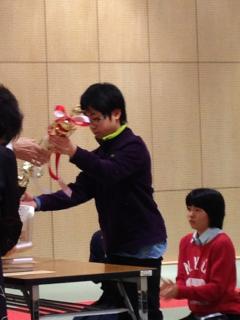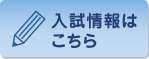修学旅行の事後学習として、中学3年生で行っている「コミュニケーション授業」。今回は2組・6組を担当していただいている、吉田小夏さんの1回目の授業を紹介します。
吉田小夏さんは、劇団「青☆組」を主宰し演劇活動を行っています。近年では、創作活動に加え、外部劇団への脚本提供、国際交流、そしてワークショップ講師など、多角的な活動を行っており、本校でのワークショップ講師も今年で3年目となります。


続きを読む "中学3年 コミュニケーション授業7" »
京都大学理学部主催の「数学の森」で2年連続の銅賞受賞、本校の前数学部部長、そして海城&YSFH数学定期交流会などで目覚ましい活躍を見せる高校2年の恩田直登君が、自身のオリジナル論文をインドの査読付き国際数学雑誌である
Journal of algebra and number theory: Advances and Applications
に投稿し掲載されました。
投稿誌は、米国数学会および欧州数学会にてその内容がレビューされるものゆえ価値は高く、加えて高校生の論文が国際数学雑誌に掲載されることは希代のことと申せましょう。
すでに掲載誌のHPには、恩田君の論文
A note on certain relations between the Fibonacci sequence and the Euclidean algorithm
が電子ジャーナルとして配信されています:
http://www.scientificadvances.co.in/artical/3/133 を参照のこと。
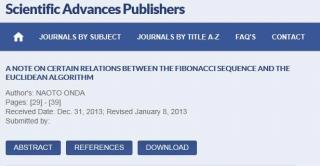
〈投稿誌のHPより. NAOTO ONDAの名前が見られる〉

〈昨年末、本校数学科ゼミコーナーにて、論文投稿前の最終チェックをする恩田君〉
続きを読む "高2前数学部部長、インドの国際数学雑誌に論文掲載される!" »
塩野直道先生は、今日、伝説の算数教科書と呼ばれ、昭和10年から18年まで使われた「尋常小学算術」(通称「緑表紙」)の編纂者です。
この教科書が「伝説」とされるゆえんは、「数理思想の開発」と「日常生活の数理的訓練」を目的に掲げ、カラーの絵を多用して視覚的に数の概念を把握できるよう工夫がなされるなど、それ以前の教科書から面目を一新した画期的なものであったからです。
この教科書は世界的にも評価が高く、昭和11年ノルウェーのオスローで開催された国際数学者会議では大変な関心が寄せられた、との史実があり、現在、皆さんが使用している教科書の装丁と精神の源流がこの緑表紙だといっても過言ではない、との評が少なくありません。
その塩野直道先生を記念して創設された算数・数学研究のコンクールが「塩野直道記念」で、その第1回受賞作品の発表がさる1月23日に行われました。
東京大学総長であった吉川弘之氏を理事長とする「RIMSE(財団法人理数教育研究所)」が鳴り物入りで開始したビッグタイトルだけに、応募総数はこの種のコンクールとしては異例といえる小中高合せて実に9132件にわたりました。
そのなかで、高校生部門の賞は約10個用意されており、その審査もまず各地域(ブロック)で選考して当落を決定した後,中央審査を経て,受賞作品を決定するという厳正さでした。今回は、高校生部門は合計13作品に賞が与えられ、その中の2作品で、本校高2年の山口哲君,井上立之君が奨励賞に輝きました。

〈表彰を受ける山口君〉
続きを読む "高2生2名が塩野直道記念奨励賞を受賞!" »
今年度で3回目となります中学3年生の「コミュニケーション授業」。年が明けてから、すべてのクラスの活動がはじまっています。今年も芸術家の方をお招きし、修学旅行の事後学習として各クラス100分×3回の授業を行い授業の中で修学旅行を振り返りながら、最終的に班ごとに演劇の作品を創り発表会を行っています。すでに発表会を終了しているクラスもありますが、発表会の様子は最後にまとめてご報告することにして、今回は4組と8組の最初の授業の様子をご報告します。
4組、8組は劇作家・演出家の大池容子さんを講師にお招きしています。大池さんは「うさぎストライプ」を主宰し、アトリエ春風舎芸術監督を務められています。

続きを読む "中学3年 コミュニケーション授業6" »
新しい年が明け、かるたシーズンの到来です。まずは新年1月5日に行われた新春大会A〜C級の部から、早速の昇段者が出ました。
高1伊藤がB級二段に、高2瀬川がA級四段にそれぞれ昇段です。ついに海城かるた部からA級選手が出るという嬉しいニュースに、部員たちの士気もぐんと上がりました。
続いて、1月11日新春大会D,E級の部では、高1水野がD級準優勝でC級初段に昇段、E級の部では中2平山が優勝、同じく中2の板垣が準優勝、鹿野と渡辺(慶)が三位で、この四人がD級に昇級しました。また、中3妹尾、中2佐藤(気)は惜しくも四位で昇級を逃しましたが、海城かるた部だけで七人という大量入賞となりました。
続く1月12日、東京東会大会E級の部では、昨日の新春大会での昇級者に後を取るまいと奮起した部員が大健闘し、中2鈴木(虎)が優勝、中3妹尾が準優勝、中3谷が三位と、この三人がD級に昇級し、この二日間で中学かるた部E級部員が七人D級に昇級するという、日々の熱心な練習の成果がここへきて一気に開花した結果となりました。
さらに翌週の東京東会大会D級の部では、先週の新春大会でD級に昇段したばかりの中学生が想像以上の奮闘を見せ、なんと、中2平山がD級優勝してC級初段に昇段しました。平山は七日間で二階級昇級、二冠達成という異例のスピード昇級で、中2部員初の有段者となりました。
そればかりか、同じく先週D級に昇級したばかりの中2板垣、渡辺(慶)も四位入賞という大健闘ぶりで、とくに板垣は最後二枚差での惜敗となり、昇級にあとほんの一歩のところまで迫り、海城中学かるた部がD級でも十分戦えるということを証明しました。
中学かるた部はこの大会をもって代替わりとなり、新部長に板垣、新副部長に渡辺の新体制のもと、ますます意気盛んに、3月の学生選手権に向けて切磋琢磨しています。
高校のほうはまだしばらく大会シーズンが続きますので、さらなる躍進をご期待下さい。
※かるたの試合は、数百名の参加選手を64名以下ずつの組に分け、各組のトーナメント戦で行われます。三位入賞以上で昇級、昇段となり、優勝するまでには丸一日かけて六試合を勝ち抜かなければなりません。基本的に同校の選手は違う組になるため、同じ学校から優勝者が複数出るということも可能です。
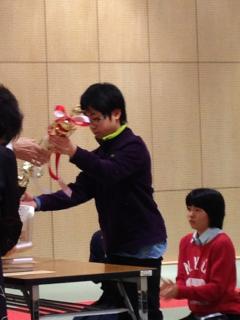
続きを読む "競技かるた部活動報告 その13 新春かるた会で中学生大活躍!" »
2月17日、東京都市大学横浜キャンパスで開催された第46回生物研究の集いに生物部16名で参加してきました。生物研究の集いは毎年開催され、今年で46回目になる歴史ある発表会で、都内私立の生物部を中心に参加者は350名以上にもなります。他の学校の研究発表が聞けたり、自分たちの研究を発表をし、質問や意見がもらえたりと生徒たちにとって、とてもよい刺激ををもらえる場所となっています。
生物部では、口頭発表で「都市部のスズメと電柱機器のカンケイ」、展示発表で「骨格標本と土壌動物」を発表しました。口頭発表では、昨年の発表では原稿を見ながら発表していた生徒が、今回は原稿を見ず、堂々と発表していました。また研究内容も統計的な手法を用いたデータ解析も行っており、昨年から、数々の学会など多くの発表の場面を経験してきたので、研究内容も発表方法もどちらも成長した姿が見られてよかったです。
展示発表の方では、タヌキ、アライグマ、ハクビシンの骨格標本を展示しました。横浜まで運搬するための梱包などを生徒なりに考えて、無事に運び、展示することができました。また、土壌動物では近くの公園で採取したカニムシやクモを展示しました。多くの人たちが発表を見てくださり、楽しく意見交換ができたようです。
今回、先輩たちや他校の発表を見た中1や中2の生徒が盛んに研究をして、きちんと発表できるようになることを期待しています。
(生物部 顧問)

発表会場前のフロアで楽しく記念撮影!
続きを読む "生物部 第46回生物研究の集いに参加" »
 地学部 生徒理科研究発表会参加
地学部 生徒理科研究発表会参加