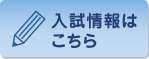1学期 医学部小論文・面接講座 特別企画 報告
1学期 医学部小論文・面接講座 特別企画 報告

1学期の講習全8回の最終回となる6月29日(土)に、校外からスペシャル・ゲストとして、看護師の瀬野佳代氏(三恵病院看護副部長)をお招きし、「チーム医療の中での本当の専門性とは―看護師から見た医師への期待―」と題してお話しいただきました。
瀬野さんはまず、看護師生活の中で、多くの優れた医師との出会いがあり、これまで看護師を続けてこられたのも、その中で自分が様々なことを学び、励まされてきた具体的な経験を話されました。それらを踏まえた上で、今日は、精神看護の現場の中で考えてきた点に限定してお話しさせていただくつもりですと、口火を切りました。
その要旨を、ポイントを絞って、以下簡単にまとめます。
医師は、患者との関係はもとより、医療従事者の中でもその地位は最も高く、たとえば看護師が医師に何か言う場合でも「「上申する」と言う表現を使っていた時代もあった。それは反面、医師がすべての問題を抱え込み、責任を取る「孤独な存在」でもあったのだろう。しかし、現在では<患者の困りごと>を改善し、いかにその生活支援をしていくかという点を中心にして、医師、看護師、精神保健福祉士、薬剤師、作業療法士、そして患者本人、家族などがチームの構成メンバーとして関わっていくことが、多くの医療機関で意識されてきている。
それを前提に、チーム医療での医師の専門性としての役割は、主として4つあるのではないかと考えている。
まず第1に何と言っても、患者の病気に対するきちんとした診断と治療方針を決められる専門的な力量の必要性である。他のメンバーの様々な意見を聞く必要があるにしても、最終的な治療方針を決定するのは,医師なのである。