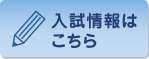中学2年生 コミュニケーション授業〜最終週〜
中学2年生 コミュニケーション授業〜最終週〜

「この授業をやっていただいて本当によかった…。」心の底から思えた瞬間だった。
第3週目。こーたさんは、演じ終えた生徒たちに感想を求めていた。「ゲストの方にお話を伺って感じたことをどうぞ」と言う具合に。その質問に対して、ある生徒が次のように答えたのだ。ちなみにこの生徒のグループは、ゲストの方が経験した戦時中のエピソードを演劇の軸に据えていた。
「う〜ん…。何て言ったらいいんだろ…。戦争の話を伺ったんですけど…。あまりに重い話で…。…簡単に言葉にできないっていうか…。………とにかく…決して忘れちゃいけないんだなって…そう思いました。」
このグループがお話を伺ったゲストの方は、お話していただいた直後(第2週目)に次のように語っていた。
「実は私戦争の話ってこれまでず〜っと話すこと避けてたんですよ。だってあまりに生々しくてね。話してるうちにこっちもあの時のつらいなんだかんだを思い出しちゃうし。それに聞く方だって、それに付き合わされちゃたまんないだろうって。そんな私が戦争の話、今みたいにするようになったのは、孫がきっかけなんですよ。小学生になった孫が宿題かなんかで戦争の話をお年寄りに聞いてこいって。参ったなあなんて思いながら、話してあげてると、孫がとにかく真剣に聴いてくれて。そん時思ったんですよ、私たちが話さなきゃ、若い人たちに戦争のつらさっていうのかな、そんなのが伝わっていかないんじゃないかって。だから海城さんからお話いただいた時に、孫に話したみたいな戦争の話でもしようかなってね。うちらそれしか話せないしね。」
私にとっても、そして生徒たちにとっても、「伝える」ことと「受け取る」こと、この2つの行為について、考えさせられた3週間だったように思う。生徒たちが最後に挑戦した「聞き書き」の演劇化、これはまずゲストの方が「伝え」ようとしたメッセージを「聞き書き」を作成することで各自が「受け取ろ」うと努力し、それをどうやったら、同じ話を聴いていない仲間に「伝える」ことができるか、それをグループで試行錯誤する、この一連の流れに意味があったのではないだろうか。つまり出来上がった「演劇作品」に意味があるのではなく、それを制作するプロセスにこそ意味があったと思うのだ。
発表の一つ一つに私は大げさではなく感動を覚えた。それはもちろん演技のすばらしさに魅了されたわけではない。「受け取った」ものを一生懸命他者へ「伝え」ようとする生徒たちの真摯な姿勢に魅了されたのである。同じものを共有できたときに感じるあの「一体感」、それを感じさせてくれた発表が想定していた以上にあったのが何より嬉しかった。冒頭に紹介した生徒が属するグループの発表、それもこの一つだったというわけだ。
「一体感」を得るために、必死に「伝え」合い、そして「受け取り」合う、そのことの難しさと大切さが体感できた、それが何よりの収穫だった。これからの日常にそれを活かしてもらえれば幸いである。